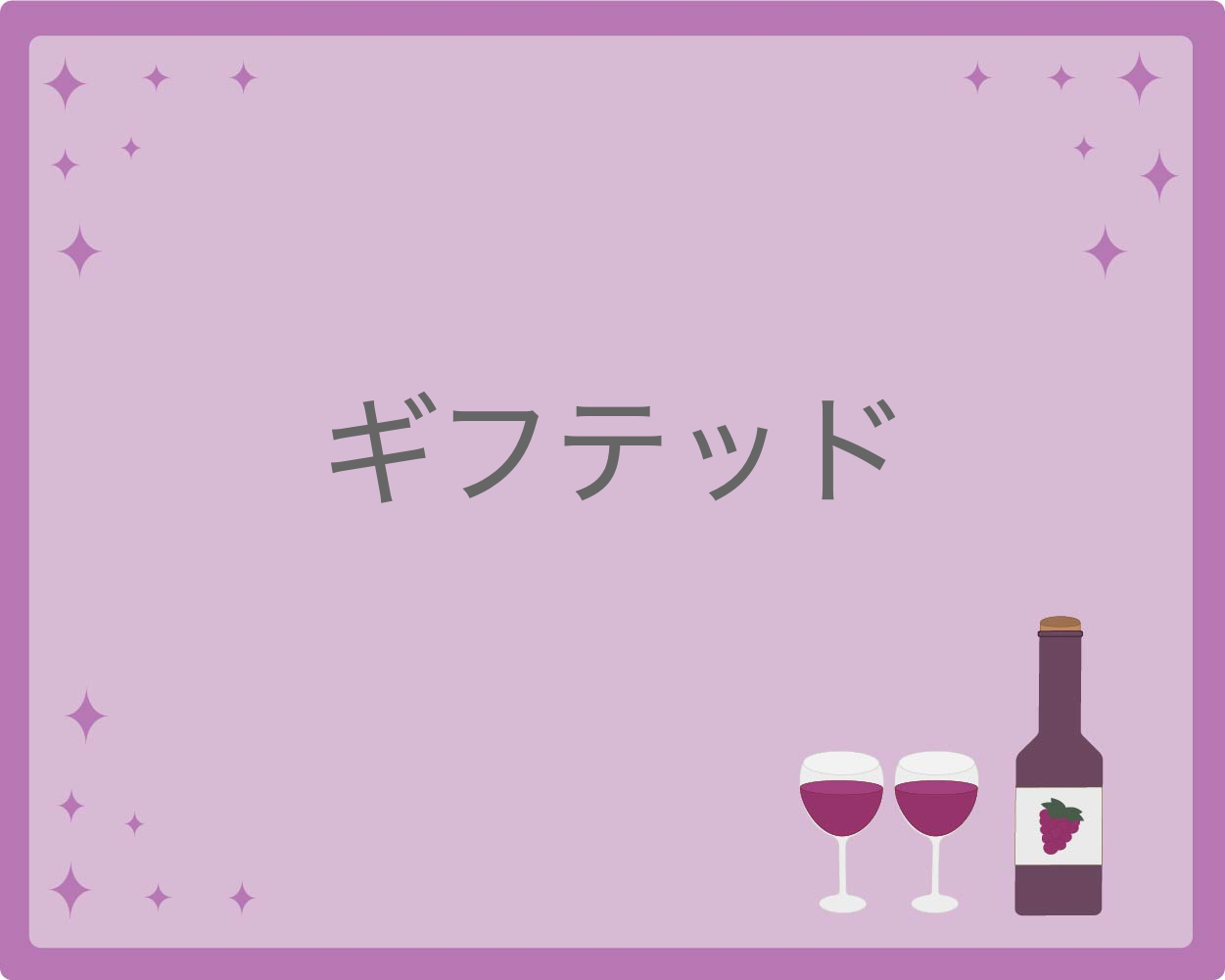ギフテッドの才能を伸ばす教育、進んでいるんだね。

でも才能が原因で孤立するなんて、悲しい話だ。

能力を活かすには、社会の理解が不可欠だな。

環境を整え、才能の開花を支えることが大切だ。
「ギフテッド」という言葉に、どのようなイメージを持つでしょうか。多くの人は、天才や秀才、生まれながらにして特別な才能を持つ子どもたちを思い浮かべるかもしれません。その認識は間違いではありません。ギフテッドとは、知的能力や芸術、運動といった特定の分野において、同年代の子どもたちより著しく高い能力を示す子どもたちを指します。
彼らは、大人が頭を悩ませるような複雑な問題をいとも簡単に解いてしまったり、誰も思いつかないような独創的なアイデアで周囲を驚かせたりします。しかし、その輝かしい才能の光の裏には、見過ごされがちな影の部分も存在しているのです。
近年、テレビやインターネットでギフテッドに関する情報に触れる機会が増えました。IQ141を持つ小学生が、その才能ゆえにクラスメイトから嫉妬され、いじめの対象になってしまったという痛ましいニュースは、記憶に新しいかもしれません。一方で、驚異的な能力を持つ「本物のギフテッド」を紹介する動画が注目を集めるなど、社会的な関心は高まっています。
これらの事象は、ギフテッドという存在が広く知られるようになった証拠であると同時に、彼らが直面する課題や、その才能を正しく伸ばすための支援がいかに重要であるかを私たちに問いかけています。この記事では、ギフテッド教育の現状と未来に焦点を当て、その光と影の両面から深く掘り下げていきます。
ギフテッド教育の最前線:才能を伸ばすための挑戦

ギフテッド教育の世界は、常に新しい挑戦と進化を続けています。子どもたちの類まれな才能をいかにして見出し、育んでいくか。その最前線では、ユニークで先進的な取り組みが次々と生まれています。
教育大学ギフテッド高等学校の挑戦
ギフテッド教育の現場を牽引する存在として、教育大学ギフテッド高等学校の取り組みが挙げられます。同校は先日、10年生の入学試験の点数を公表し、大きな注目を集めました。IT、文学、英語といった専門クラスが軒並み高得点を記録し、系列の専門高校の中で最高得点を叩き出したのです。
この結果は、同校の教育プログラムが非常に高い水準にあり、生徒たちの能力を最大限に引き出すことに成功していることを示唆しています。単なる知識の詰め込みではなく、生徒一人ひとりの才能を深く掘り下げる教育の成果と言えるでしょう。
また、同校は入学時期の調整といった柔軟な対応も行っています。これは、生徒たちが市内の他の専門学校への入学手続きを完了できるよう配慮したもので、進路選択の幅を広げるための重要な試みです。
ギフテッド教育の本質は、学力を高めることだけではありません。生徒一人ひとりの個性と才能を深く理解し、尊重しながら、彼らが自らの未来を切り拓くための力を育むサポートを提供することにあるのです。
Gifted Schoolの革新的な取り組み
ギフテッド教育の分野で、もう一つ注目すべき存在が「Gifted School」です。このスクールは、発達に凸凹のある子どもたちを対象に、完全オーダーメイドの授業を展開していることで知られています。

発達に凸凹があるって、どういうこと?

得意なことと苦手なことの差が大きい状態のことです。ギフテッドの子どもたちによく見られる特性の一つなんですよ。
そして2025年6月10日には、幼児から社会人までを対象とした「完全オーダーメイドAI教育プログラム」の提供を開始すると発表しました。このプログラムは、AI技術を駆使して生徒一人ひとりの学習進度や理解度、興味に合わせてカリキュラムを最適化するもので、従来の画一的な教育とは一線を画す革新的なアプローチです。
さらに、高IQ集団であるMENSAの会員が直接指導するAI教育プログラムも提供しており、幅広い年齢層に最先端の学びの機会を提供しています。これは、ギフテッド教育が子ども時代だけで完結するものではなく、生涯にわたる学習と成長をサポートするものであるという考え方を示しています。
オンラインスクールとしても活動の幅を広げており、2025年度の夏期特別講習では、「好き」を「才能」に変えることをテーマに掲げ、生徒たちの知的好奇心や探究心を刺激するプログラムを用意しています。Gifted Schoolの取り組みは、既存の教育の枠組みにとらわれず、個々の才能を最大限に開花させることを目指す、未来の教育の形を提示していると言えるでしょう。
ギフテッド甲子園と新たな才能発掘の形
ギフテッドの才能を発掘し、伸ばす試みは、学校や専門機関の中だけで行われているわけではありません。近年、新たなプラットフォームとして注目を集めているのが、ライブ配信アプリTikTok LIVEで開催される「ギフテッド甲子園」です。
このイベントでは、トップライバーたちが「ギフティング(投げ銭)」の額を競い合い、日本一を目指します。これは一見、教育とは無関係に見えるかもしれません。しかし、自分の得意なことや表現力を通じて人々を魅了し、評価を得るという点で、才能を可視化し、社会的に価値を与える新しい形と言えます。
「ギフテッド甲子園」の開催は、才能の定義が多様化し、それを育むためのプラットフォームが様々な形で生まれていることを象徴しています。学問や芸術だけでなく、コミュニケーション能力やエンターテインメント性といった多様な才能が、新しいテクノロジーを通じて評価される時代が到来しているのです。
輝かしい才能の裏側:ギフテッドが直面する困難と課題

優れた才能を持つギフテッドですが、その非凡さゆえに、多くの困難に直面することも少なくありません。彼らが抱える問題は、個人の内面だけでなく、周囲の環境や社会との関わりの中に根差しています。
社会的な理解の不足という壁
ギフテッドが直面する最も大きな壁の一つが、社会的な理解の不足です。彼らの突出した能力や独特の思考プロセスは、周囲の人々にとって理解しがたいものとして映ることがあります。その結果、誤解や偏見にさらされてしまうのです。
例えば、学校の授業が簡単すぎると感じたギフテッドの子どもが、退屈しのぎに別のことを始めたり、教師に挑戦的な質問をしたりすることがあります。しかし、その行動の背景にある知的好奇心や探究心が理解されず、単なる「問題児」や「落ち着きのない子」というレッテルを貼られてしまうケースは後を絶ちません。
画一的な教育現場での葛藤
現在の日本の公教育システムは、多くの場合、平均的な学力の子どもたちを基準に設計されています。そのため、ギフテッドの子どもたちの突出した能力や知的好奇心を十分に満たすことが難しいのが現状です。

みんなと同じ授業を受けるのは、ギフテッドの子には退屈なのかな?

例えるなら、大学生が小学校の算数の授業を毎日受けさせられるようなものかもしれません。知っていることの繰り返しは苦痛に感じてしまうんです。
画一的な授業内容、能力に応じたクラス分けの不足、知的好奇心を刺激する課題の欠如。こうした環境は、ギフテッドの子どもたちから学ぶ意欲を奪い、才能を伸ばす機会を閉ざしてしまう危険性をはらんでいます。彼らにとって、学校が苦痛な場所になってしまうことも少なくないのです。
才能が引き起こす「いじめ」という悲劇
冒頭でも触れたように、ギフテッドの才能が、時として他者からの嫉妬や攻撃の対象となることがあります。特に、同調圧力が強い子どもの世界では、「出る杭は打たれる」という状況が生まれやすいものです。
「あいつだけ先生にひいきされている」「自慢しているみたいで気に入らない」。そうした歪んだ感情が、陰口や無視、時には暴力といった陰湿ないじめにつながります。優れた能力は本来、祝福されるべきものですが、それが原因で深い心の傷を負ってしまうという悲しい現実が存在するのです。
未来への羅針盤:ギフテッドを社会全体で支えるために

ギフテッドの子どもたちがその才能を存分に発揮し、幸福な人生を歩むためには、個人の努力だけに頼るのではなく、社会全体で彼らを支える仕組みを構築することが不可欠です。未来を担う才能を守り育てるために、私たちは何をすべきでしょうか。
社会全体の意識改革と理解促進
すべての取り組みの基礎となるのが、ギフテッドに対する社会全体の正しい理解です。教育現場、メディア、そして地域社会が連携し、積極的に啓発活動を行う必要があります。
学校でギフテッドの特性について学ぶ機会を設けたり、メディアが成功事例だけでなく彼らが直面する課題についても継続的に報道したりすることで、少しずつ社会の意識は変わっていきます。「変わった子」ではなく「特別な才能を持つ子」として認識することが、支援の第一歩となるのです。
教育現場に求められる柔軟な改革
教育現場には、より柔軟で多様な対応が求められます。ギフテッドのニーズに応えるためには、画一的なシステムからの脱却が必要です。
例えば、習熟度別のクラス編成(プルアウト・プログラム)、特定の分野を深く学べる特別授業の設置、専門家や大学の研究者と連携したメンター制度の導入などが考えられます。子どもたちの「もっと知りたい」という意欲を刺激し、才能をさらに伸ばせる環境を整えることが急務である。
一人ひとりに寄り添う個別支援の充実
ギフテッドと一言で言っても、その特性や抱える課題は一人ひとり異なります。そのため、個々の状況に応じたきめ細やかな支援体制の充実が重要です。
専門のカウンセラーによるメンタルケア、学習面でのサポート、そして将来のキャリアを見据えた進路相談など、多角的なサポートが必要です。彼らが抱える孤独感やプレッシャーを和らげ、安心して自己肯定感を育めるようなセーフティネットを社会が用意しなければなりません。
才能を社会に活かすプラットフォームの構築
育まれた才能を社会で活かすための出口戦略も重要です。ギフテッドが自身の能力を社会貢献につなげられるようなプラットフォームを構築することが、彼らのモチベーションを高めることにもつながります。
ギフテッドの特性を理解した上で積極的に採用を行う企業を増やすことや、彼らの独創的なアイデアを事業化するための起業支援プログラムなどを提供すること。こうした取り組みが、才能を社会全体の財産として活かす道を開きます。
最も身近な支援者、家族へのサポート
ギフテッドの子どもたちにとって、最大の理解者であり支援者であるのは、多くの場合、家族です。しかし、その子育ては喜びであると同時に、大きな戸惑いや負担を伴うこともあります。
子どもの才能をどう伸ばせばいいのか、学校との関係はどう築けばいいのか。そうした悩みを共有し、情報交換ができる保護者同士のコミュニティを支援したり、専門家によるペアレント・トレーニングの機会を提供したりすることも、子どもたちの健やかな成長を支える上で非常に有効です。
まとめ:すべての才能が開花する社会を目指して
ギフテッド教育は、一部の特別な才能を持つ子どもたちのためだけのものではありません。それは、一人ひとりの人間の可能性を信じ、それを最大限に引き出すことで、多様な才能が共存し、尊重される社会を築くための重要な羅針盤です。
教育大学ギフテッド高等学校やGifted School、ギフテッド甲子園といった先進的な取り組みは、ギフテッド教育が新たなステージへと進化していることを示しています。しかしその一方で、社会的な理解不足や画一的な教育、いじめの問題など、彼らの才能の開花を阻む課題も依然として山積しています。
ギフテッドという存在を支えるためには、社会全体の意識改革、教育現場の柔軟な対応、一人ひとりに寄り添う個別支援、才能を活かす場の創出、そして家族へのサポートという、多層的なアプローチが不可欠です。
未来を創造する力を持つギフテッドたちが、その才能という羅針盤を頼りに、自らの可能性を信じて大海原へと漕ぎ出せるように。彼らの航路を明るく照らし、時には嵐から守る灯台となることこそ、私たち社会に課せられた大切な責務ではないでしょうか。
参考リンク